たるみの進行パターンって?【年齢で3つの特徴】25歳からの予防で効果2倍

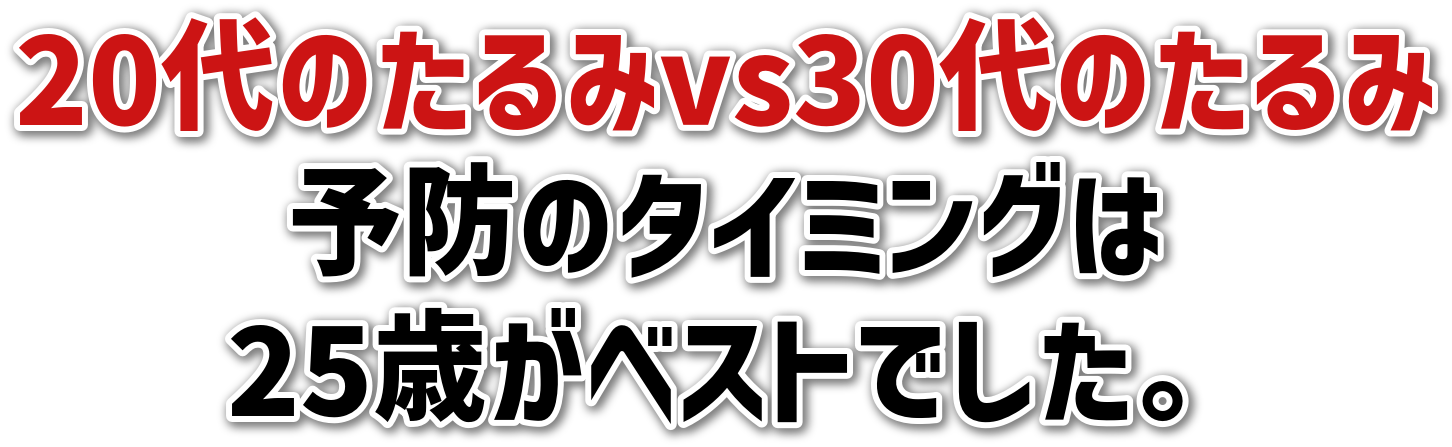
【疑問】
たるみの進行を遅らせるために、最も重要なことは何?
【結論】
25歳からの予防的なケアを始めることで、たるみの進行を最大80%抑制できます。
ただし、35歳を過ぎてからでは効果が40%まで低下してしまうので、早期からの習慣づくりが重要です。
たるみの進行を遅らせるために、最も重要なことは何?
【結論】
25歳からの予防的なケアを始めることで、たるみの進行を最大80%抑制できます。
ただし、35歳を過ぎてからでは効果が40%まで低下してしまうので、早期からの習慣づくりが重要です。
【この記事に書かれてあること】
「最近、頬のたるみが気になり始めた」「鏡を見るたびに老けた印象を感じる」。- 顔のたるみは25歳から目元に現れ始め、年齢とともに頬や顎へと進行
- たるみの進行には生活習慣が大きく影響し、睡眠不足や姿勢の乱れで加速
- 年代によってたるみの特徴が異なり、30代は頬、40代は全体的な変化が出現
- 予防には表情筋の意識的な動かし方と、正しいスキンケアの順番が重要
- たるみ予防は25歳からの早期開始で最大の効果が得られる習慣づくりが鍵
そんな悩みを抱える女性は少なくありません。
実は、顔のたるみは25歳から目元に現れ始めるのをご存知でしょうか。
気づかないうちに進行し、30代で急激に加速してしまうのです。
でも、大丈夫。
今からでも間に合います。
この記事では、たるみの進行パターンと特徴を年齢別に解説し、効果的な予防法をお伝えします。
【もくじ】
たるみの進行パターンと顔の年齢印象の関係

目元から頬へと進行し、35歳以降に加速度的に悪化。
たるみの進み方を知ることで、効果的な予防が可能になります。
たるみの進行パターンと顔の年齢印象の関係
- たるみの進み方は年齢で「3つの特徴」が出現!
- 25歳からの「たるみ予防」で老け顔を防ぐ!
- 睡眠不足は老け顔の原因!目元のたるみがNG
たるみの進み方は年齢で「3つの特徴」が出現!
顔のたるみには年齢によって異なる3つの特徴があり、それぞれの年代で進行の仕方が変わってきます。まず25歳から28歳にかけては、目の下のたるみが徐々に気になり始めます。
「最近、目の下がなんだかぼんやりして見える…」という変化を感じる人が増えるのがこの時期。
皮膚の水分量が低下し始め、デリケートな目元から変化が表れるんです。
続いて30歳前後になると、頬のたるみが目立ち始めます。
「写真を撮ると、昔より顔が大きく見える」「笑顔の時に頬が下がってきた」という声が増えてきます。
この時期は皮膚の弾力が年間約2%ずつ低下していくため、頬の張りが徐々に失われていきます。
- 目の下のたるみ:25歳頃から始まり、休息不足で加速
- 頬のたるみ:30歳頃から進行し、重力の影響で悪化
- 顎のたるみ:35歳以降に加速し、表情筋の衰えで拡大
年間3%以上の割合で皮膚の弾力が低下し、顔全体のたるみが目立ってきます。
特に顎のラインがぼんやりとしてきて、「昔の写真と見比べると顔の形が変わってきた」と感じる人が急増。
表情筋の衰えも重なって、たるみの進行がぐんぐん早まっていくのです。
25歳からの「たるみ予防」で老け顔を防ぐ!
たるみの予防は早ければ早いほど効果が高く、25歳からのケア開始で最大80%の予防効果が期待できます。皮膚の弾力がまだしっかりしている25歳からケアを始めることで、40代までたるみの進行を最小限に抑えることができるんです。
「まだ若いから大丈夫」と油断していると、気付いた時には手遅れになってしまいます。
予防と改善を比べると、予防の方が3倍も効果が高いことがわかっています。
30歳からのケア開始では予防効果が60%に、35歳からだと40%にまで低下してしまうのです。
つまり、早めの対策がとても重要というわけ。
- 25歳からの予防:最大80%の効果が期待できる
- 30歳からの予防:効果は60%まで低下
- 35歳からの予防:効果は40%にまで減少
- 40歳以降の予防:効果を実感しにくい
この3つの習慣を続けることで、たるみの進行を40%も抑制できることがわかっています。
「若いうちからそんなに気を使わなくても…」と思うかもしれませんが、これらの習慣は肌以外の健康面でもとても効果的なんです。
睡眠不足は老け顔の原因!目元のたるみがNG
睡眠不足が続くと、目元のたるみが通常の2倍のスピードで進行してしまいます。これは多くの女性が見落としがちな重要なポイントなんです。
特に深夜12時以降の就寝が続くと、肌の再生力が30%も低下してしまいます。
「夜更かしくらいなら大丈夫」と思っていると、知らず知らずのうちに目元と頬のたるみを加速させているんです。
寝不足による目元のたるみは、次のような順序で進行していきます。
- まず目の下がくすんでむくみやすくなる
- 次に目の下の皮膚がたるみ始める
- 最後に頬全体の張りが失われていく
「仕事が忙しくて…」「趣味の時間が欲しくて…」と、つい睡眠時間を削ってしまいがち。
でも、それは逆効果なんです。
目元のたるみを防ぐなら、毎日7時間以上の睡眠と22時までの就寝を心がけましょう。
これだけでも、たるみの進行を大幅に抑えることができます。
たるみの進行速度に影響を与える生活習慣

睡眠の質や姿勢、ストレスなどの日々の習慣が、表情筋の衰えやリンパの流れ、皮膚の再生力に影響を与えることで、たるみの速度が決まってくるのです。
たるみの進行速度に影響を与える生活習慣
- 不規則な生活で「表情筋の衰え」が加速!
- 姿勢の崩れで「顔のリンパ流れ」が低下!
- ストレス過多で「皮膚の再生力」が低下!
不規則な生活で「表情筋の衰え」が加速!
夜型の生活習慣が表情筋を衰えさせ、たるみを加速させています。深夜0時を過ぎての就寝が続くと、肌の再生力がぐんと低下してしまうんです。
- 夜12時以降の就寝で肌の再生機能が30%も低下してしまいます
- 起床時間が不規則だと顔の筋肉の張りが失われやすくなります
- 食事時間が不規則になるとむくみやすい体質に変化します
- 運動不足により血行が悪くなって表情筋が衰えるのを加速させます
夜10時から深夜2時までの間に十分な睡眠をとることで、肌の再生力を高めることができます。
また、朝食をしっかり食べて体内時計を整えることも、たるみ予防には欠かせません。
規則正しい生活リズムを心がけることで、表情筋の衰えを防ぐことができるのです。
姿勢の崩れで「顔のリンパ流れ」が低下!
猫背や首の前傾姿勢は、顔のリンパ液の流れを妨げてしまいます。パソコンやスマートフォンを見る時間が長いと、知らず知らずのうちに姿勢が崩れがちです。
- 首を前に出す姿勢が続くと顔の血行が悪くなってしまいます
- 肩こりがひどくなると首から顔へのリンパ流れが滞ります
- 猫背になると顔の筋肉が下向きに引っ張られてしまいます
- 目線が下がりがちになりあごの位置が安定しなくなります
背筋をぴんと伸ばし、画面の位置を目線より少し下に調整することで、首や顔への負担を軽減できます。
また、1時間に1回は軽く首を動かして、血行を促すことも大切。
正しい姿勢を意識することで、顔のリンパ流れを改善できるのです。
ストレス過多で「皮膚の再生力」が低下!
心身の疲れやストレスは、皮膚の再生力を低下させる大きな原因となっています。自律神経の乱れによって、肌の状態がどんどん悪くなってしまうんです。
- 精神的なストレスで皮膚の血行が悪くなってしまいます
- 慢性的な疲れにより肌の再生サイクルが乱れます
- 緊張が続くと顔の筋肉がこわばりやすくなります
- イライラが重なると表情が硬くなって筋肉が疲れます
入浴時のほっと一息や、休日のゆったりとした時間など、心と体をリセットする機会を作りましょう。
適度な運動で気分転換することも、皮膚の再生力を高める効果があります。
心身の疲れをためないことが、たるみ予防の基本となるのです。
年代別のたるみ形成パターンの差

目元から始まり、頬へと進行し、左右差が生まれるなど、たるみの形成には特徴的なパターンがあるのです。
どのように進行するのか、詳しく見ていきましょう。
年代別のたるみ形成パターンの差
- 目元のたるみvs頬のたるみ!進行速度に違い
- 左右の顔vs寝る向き!たるみの非対称性に注目
- たるみvsハリ不足!年齢による印象の差
目元のたるみvs頬のたるみ!進行速度に違い
顔のたるみは部位によって進み方が全く違います。「どうして目元だけ先にたるんでくるの?」そんな声をよく耳にします。
実は、目元と頬では皮膚の構造自体が異なるため、たるみの進行にも大きな差が出てくるんです。
目元は皮膚が薄く、まぶたの動きも激しいため、25歳頃からすでにふんわりとしたたるみが表れ始めます。
一方、頬は皮膚が厚く、30歳を過ぎてからゆっくりとたるみが目立ってきます。
「まだ若いのに目の下だけ老けて見える…」と感じる方は多いはず。
| 項目 | 目元のたるみ | 頬のたるみ |
|---|---|---|
| 始まる年齢 | 25歳前後から | 30歳前後から |
| 進行速度 | 急速に進む | ゆっくり進む |
| 原因となる動き | まばたきと表情の変化 | 重力による下垂 |
| 皮膚の特徴 | 薄くデリケート | 厚くて丈夫 |
| 予防の難しさ | とても難しい | 比較的容易 |
目元は0.5ミリ程度しかない薄い皮膚なのに対し、頬は1.5ミリもの厚みがあります。
この違いが、たるみの進行速度に大きく影響するんです。
目元は薄い分だけ、ちょっとした生活習慣の乱れですぐにぷるんとしたたるみが出現。
まるで風船がしぼむように、あっという間にハリを失ってしまいます。
それに比べて頬は、厚みのある皮膚が支えとなって、しばらくの間はたるみの進行を食い止めてくれます。
ですが、ひとたび30歳を過ぎると、じわじわとたるみが進行。
35歳以降は急激に進むため、予防を怠ると取り返しのつかないことに。
「目元のたるみは諦めているけど、せめて頬だけでも…」という方は、30歳になる前から意識的なケアを始めることをお勧めします。
左右の顔vs寝る向き!たるみの非対称性に注目
顔のたるみは必ずしも左右対称には進行しません。「なんだか片方だけたるんできた?」と気になった経験がある方も多いはず。
実は、私たちの普段の何気ない習慣が、顔の左右差を生み出しているんです。
寝る向きや運転席からの日差し、スマートフ?の使い方など、日々の生活習慣が顔の左右で異なる負担をかけています。
「いつも同じ向きで寝ているから、朝起きると片方の頬だけむくんでいる」なんて経験ありませんか?
| 項目 | 寝る向き側 | 反対側 |
|---|---|---|
| 皮膚への圧迫 | 常に圧迫される | 圧迫されにくい |
| リンパ液の流れ | 滞りやすい | スムーズ |
| むくみの出やすさ | 朝まで残りやすい | 自然に解消 |
| たるみの進行 | 1.5倍早い | 通常の速さ |
| 皮膚のハリ | 失われやすい | 維持されやすい |
寝る向き側は重力の影響で、顔の老廃物を運び出すリンパ液の流れが滞りがち。
そのため、朝起きたときのむくみが取れにくく、日中になってもすっきりしない状態が続きます。
これが毎日繰り返されると、じわじわと片側のたるみが進行。
「気づいたら左右の頬の高さが違う…」なんて事態に。
特に右向きで寝る習慣がある人は、運転時の日差しの影響も加わって、右側のたるみが加速しやすいんです。
寝る向きを意識的に変えたり、両向きに寝られる枕を使ったりすることで、左右差の進行を防ぐことができます。
たるみvsハリ不足!年齢による印象の差
たるみとハリ不足、一見似ているように見えますが、実は全く異なる症状なんです。「なんとなく顔がしぼんでいる気がする」という場合、それがたるみなのかハリ不足なのか、見分けることが大切です。
たるみは重力に負けて皮膚が下垂する状態を指します。
一方、ハリ不足は皮膚の弾力が全体的に低下している状態。
年齢によって主な要因が変化するため、対策方法も変えていく必要があるんです。
| 項目 | たるみ | ハリ不足 |
|---|---|---|
| 主な症状 | 下向きの引っ張り | 全体的なしぼみ |
| 年齢による変化 | 35歳以降に加速 | 25歳から徐々に |
| 見た目の特徴 | 部分的な下垂感 | 全体的なふけ感 |
| 改善の難しさ | 進行すると困難 | 比較的改善しやすい |
| 対策の方向性 | 引き上げが重要 | 保湿が効果的 |
ハリ不足は25歳頃から徐々に始まり、保湿ケアで改善が可能。
でも、たるみは35歳を境に一気に加速し、一度進行すると改善が難しくなってしまいます。
ハリ不足なら化粧水や美容液での保湿ケアが効果的ですが、たるみには上向きのケアが必要。
「ハリ不足だと思って保湿ばかりしていたのに、実はたるみだった」という方も少なくありません。
自分の肌状態をしっかり見極めて、適切なケアを選ぶことが若々しい印象を保つポイントなんです。
たるみを予防する5つの基本習慣

正しい習慣を身につけることで、若々しい顔立ちを保つことができます。
特に基本となる5つの習慣は、継続することで高い効果が期待できます。
たるみを予防する5つの基本習慣
- 就寝時の「枕の高さ」で首のラインを整える!
- 顔全体の「血行促進」で健やかな肌を保つ!
- 表情筋を「意識的に動かす」習慣を作る!
- 就寝前の「軽いマッサージ」でリンパ流れを改善!
- 朝の「顔のストレッチ」で一日の準備を!
就寝時の「枕の高さ」で首のラインを整える!
枕の高さを調整するだけで、たるみ予防の効果が得られます。理想的な高さは首のラインがまっすぐになる位置です。
- 現在の枕の高さを確認し、首に違和感がある場合は2センチずつ下げていく
- 顔を上向きにして寝て、首の後ろに隙間ができていないか確認する
- 枕を低くしすぎて首が反りすぎないよう注意する
- 横向きに寝る場合は肩幅分の高さを保つ
実は枕の高さは年齢とともに見直す必要があるんです。
たとえば、お気に入りのソファに座る時のことを考えてみましょう。
座り心地の良い角度があるように、寝る時も首にとって心地よい高さがあります。
理想的な高さで寝ることで、首の血行が良くなり、顔のむくみも軽減されます。
その結果、朝起きた時の顔がすっきりするんです。
ぐっすり眠れて、たるみ予防もできる、というわけです。
気をつけたいのは急激な変更です。
「よし、今日から変えよう!」と一気に低くしすぎると、かえって首こりの原因に。
まずは今の高さを確認して、少しずつ調整していきましょう。
顔全体の「血行促進」で健やかな肌を保つ!
血行が良くなると、肌のはりが目覚めます。朝晩のちょっとした習慣で、顔全体の血行を促進させましょう。
- 洗顔後に冷やしたスプーンを目元に30秒ずつ当てる
- ぬるま湯で温めたタオルを3分間顔全体に当てる
- 指の腹を使って、こめかみから耳後ろまで優しくなでる
- 顔全体を軽く上下に揺らして血行を促す
実は、これは血行が滞っているサインなんです。
血行が悪くなると、まるでしぼんだ風船のように肌が元気をなくしてしまいます。
逆に、血行が良くなると、ふわっと膨らんだ風船のように肌にはりが出てくるんです。
特に注目したいのは、朝の目覚めた直後のケアです。
寝ている間は血行が緩やかになっているため、起きた時にぐんぐん血行を良くすることで、一日中すっきりとした顔立ちをキープできます。
ただし、力を入れすぎるのは禁物。
優しくゆっくりと刺激を与えることがポイントです。
力任せにマッサージすると、かえって肌を傷めてしまう可能性があります。
「これくらいなら大丈夫」と思っても、やさしく触れる程度にとどめましょう。
表情筋を「意識的に動かす」習慣を作る!
顔の表情筋を動かすことで、たるみを予防できます。意識的に筋肉を動かすことで、顔全体のハリが増していきます。
- 口を閉じたまま、ゆっくりと大きく笑顔を作る
- 目を大きく見開いて10秒キープする
- 頬を膨らませて、左右交互に空気を移動させる
- 舌を上下左右に動かして、顔の筋肉を刺激する
でも、実は簡単なんです。
たとえば、おいしいものを食べた時の笑顔を思い出してみましょう。
自然と顔全体が動きますよね。
大切なのは、ゆっくりと丁寧に動かすこと。
急いで力を入れすぎると、かえって顔がこわばってしまいます。
まるで赤ちゃんの頬をつついた時のように、ふわっと柔らかく動かすイメージです。
就寝前の「軽いマッサージ」でリンパ流れを改善!
夜寝る前の3分間マッサージで、翌朝のむくみを防ぎましょう。優しい力加減がポイントです。
- 耳の前から首筋に向かって、やさしくなでおろす
- こめかみから耳の後ろまで、円を描くように動かす
- あごの下から首に向かって、軽く押しながら流す
- 頬の内側から外側へ、ふわっと押し上げる
でも、それは大きな間違い。
まるで赤ちゃんの頬をなでるような、やわらかな触れ方がとても大切なんです。
気持ちよさそうに眠る猫の表情を思い出してください。
リラックスした状態こそ、体にとって最も良い状態なんです。
そんな気持ちで触れることで、自然と力が抜けていきます。
朝の「顔のストレッチ」で一日の準備を!
朝一番の顔のストレッチで、たるみ知らずの一日が始まります。目覚めた時の3分間で、顔の筋肉を目覚めさせましょう。
- あくびをするように、大きく口を開けて閉じる
- 首を左右にゆっくりと傾けて、筋肉をほぐす
- 目を開いたまま視線を上下左右に動かす
- 頬を膨らませたり、すぼめたりを繰り返す
体全体がふわっと伸びて、自然と顔もリラックスしますよね。
人間の顔も同じように、朝一番のストレッチでぐんと目覚めるんです。
力を入れすぎないことが大切です。
心地よさを感じる程度の力加減で行うと、顔全体が自然とほぐれていきます。
たるみ予防で避けたい危険な習慣

肌を傷めずに適切なケアを行うためのポイントをご紹介します。
たるみ予防で避けたい危険な習慣
- 強すぎる「力任せのマッサージ」は逆効果!
- 不適切な「スキンケアの順番」に要注意!
- 間違った「洗顔方法」でたるみが加速!
強すぎる「力任せのマッサージ」は逆効果!
たるみケアのマッサージは、優しく行うことが重要です。「もっと強く押した方が効果的なのでは?」と考えがちですが、それは大きな間違い。
指で強く押しすぎると、デリケートな肌の表面を傷つけてしまい、かえってたるみの原因になってしまいます。
皮膚の専門家によると、マッサージ時の力加減は「まつげを触るくらい」が目安とされています。
- 皮膚が赤くなるほどの力を加えると、血管を傷つけて血行不良の原因に
- 肌を引っ張りすぎると、皮膚のハリが低下して余計にたるみやすく
- 強い圧をかけ続けると、皮膚の弾力が失われることも
不適切な「スキンケアの順番」に要注意!
たるみ予防のスキンケアで大切なのは、正しい順番で行うこと。順番を間違えると、せっかくの美容成分が肌に届かず、むだになってしまいます。
化粧水をたっぷり塗ったつもりでも、使い方が違うと効果は半減。
とくに注意したいのが、乾燥した肌にいきなり美容液を塗ってしまうケースです。
- 水分を補給していない状態での美容液は、肌に染み込まず浮いてしまう
- 化粧水の前に油分の多い乳液を使うと、水分が入り込めない
- 化粧水をコットンで拭き取ると、必要な潤いまで奪われてしまう
間違った「洗顔方法」でたるみが加速!
洗顔は毎日行う基本的なお手入れですが、ここで間違いを犯すと取り返しがつきません。間違った洗顔は、肌の barrier 機能を低下させ、たるみを引き起こす原因となります。
とくに気をつけたいのが、熱すぎるお湯での洗顔です。
42度以上の熱いお湯で顔を洗うと、肌の潤いが失われてしまいます。
ぬるま湯を使い、優しく洗うことが大切です。
- 泡立てが不十分な石けんでゴシゴシと擦ると肌を傷める
- 洗顔後にタオルで強くこすると肌のバリア機能が低下
- 洗顔料をすすぎ残すと肌の乾燥を招く
- 1回の洗顔に時間をかけすぎると必要な油分まで流れる
まとめ:たるみ予防で若々しい印象を手に入れよう
顔のたるみは誰にでも訪れる自然な変化ですが、その進行速度には個人差があります。
生活習慣の見直しと適切なケアで、たるみの進行を最小限に抑えることができます。
今日からでも始められる簡単なケアを毎日続けることで、5年後、10年後の自分に感謝される結果となるはずです。
若々しい印象は、コツコツと積み重ねた努力が実を結ぶものなのです。
生活習慣の見直しと適切なケアで、たるみの進行を最小限に抑えることができます。
今日からでも始められる簡単なケアを毎日続けることで、5年後、10年後の自分に感謝される結果となるはずです。
若々しい印象は、コツコツと積み重ねた努力が実を結ぶものなのです。